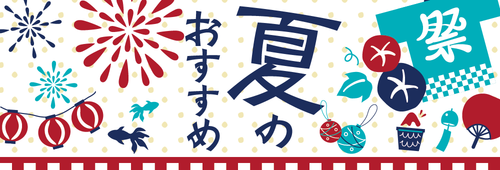麦わら帽子ができるまで。職人の手しごと、9月で販売終了です

まだまだ暑い9月。
強い日差しの下で「帽子がほしい!」と思う瞬間、ありませんか?
そんな季節に欠かせないのが麦わら帽子。
でも実は、この帽子が想像以上に手間ひまと職人の技でつくられていることをご存知でしょうか?
今回は、田中帽子店の麦わら帽子ができるまでの工程をご紹介します。
そして残念ながら、この夏季限定アイテムは9月で販売終了。
次に会えるのは来年の夏になります。
ぜひその魅力を知っていただけたら嬉しいです。
1.7本の麦の茎を手で編みます
麦わら帽子づくりは、材料の準備から始まります。
原料となるのは「麦わら真田(むぎわらさなだ)」という
7本の麦の茎を手で編んで作られたもの。
この真田を水に浸して柔らかくしてから、ようやく帽子づくりがスタートするのです。
2.円を描くように縫い進めます
柔らかくなった麦わら真田を専用ミシンで縫い合わせていきます。
スタートは帽子の中心、「渦」。
そこからぐるぐると円を描くように重ねながら縫い進めていくのだとか。
職人は途中で木型を使ってサイズを確認しながら進めます。
材料が小さくなるほど難しくなる作業で、美しい形を作るには熟練の技が必要。
一本の麦わら真田が円を描き、重なり合うことで伸縮性が生まれ、快適なかぶり心地につながっていくんです。
3.春日部の風物詩 寒干し
 提供:田中帽子店
提供:田中帽子店縫い上がった帽子は、乾いた空気の中でじっくり天日干しされます。
この工程は「寒干し(かんぼし)」と呼ばれ、春日部市では冬の風物詩にもなっているのだそう。
地面いっぱいに帽子が並ぶ光景は、職人のまちならでは。
春からのお届けに向けて、冬にしっかりと乾燥させることで型崩れを防ぎます。
4.最後の仕上げ

乾燥した帽子は、特別な金型や蒸気を使ってプレスし、クラウン(頭の部分)とブリム(つば)をデザインに合わせて成形します。
田中帽子店では毎年新しいデザインを開発しているため、豊富な型がそろっていて、多彩な帽子が生まれているんです。
その後、スベリ(汗止め)やリボンなどの装飾を一つひとつ手作業で取り付けます。
小さなリボンひとつでも帽子の印象は大きく変わり、ここでも職人のセンスが光ります。

最後は「つんつん取り」。表面に出たささくれを手で触りながら一本ずつ処理します。
これをしないと被ったときにチクチクしてしまうので、お客様が快適に使えるように欠かせない工程です。

こうして数えきれないほどの手作業を経て、田中帽子店の麦わら帽子は完成します。
夏の定番として当たり前のようにあるけれど、その裏には時間と技術、そして被る人への思いやりが込められているのです。
そして改めてですが、今年は9月いっぱいまでの販売。
まだ暑い日差しが続くこの時期に、夏の相棒として迎えてみてはいかがでしょうか。