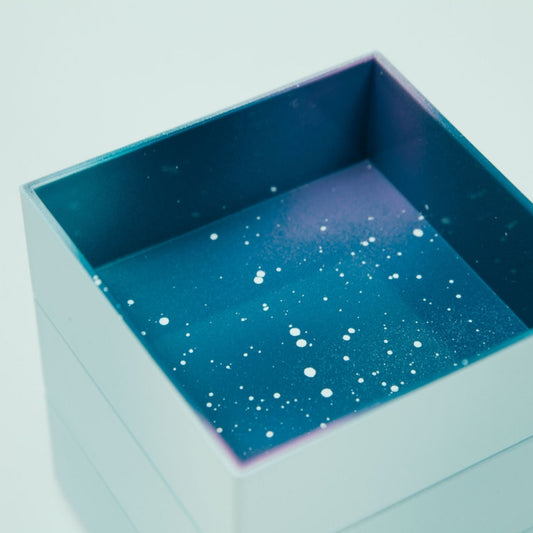甲州印伝ができるまで

甲州印伝は、染色から裁断、漆付けに至るまで、丁寧な手仕事が詰まっているんです。
今回は職人が一つ一つの工程を大切にしながら作り上げる甲州印伝の制作過程をご紹介します。
鹿革と型紙の準備

まず、甲州印伝の製作が始まるのは、鹿革の選定から。
鹿革は一頭一頭、質感が異なるため、慎重に選ばれるんです。そして選ばれた革は、ついに染色の工程へ。
まずは**芯染め(ずぶ染め)**という技法で、黒や茶、えんじ色などに染め上げていきます。
これが、甲州印伝の特徴的な色合いを作り出すための大事な一歩。
染め上がった革は、型紙を使って文様を入れるために、次の工程へと進みます。
型紙は、江戸小紋と同じく、手彫りで作られた和紙製の伊勢型紙を使用。
印伝に使われる型紙は、なんと200種類以上も揃っているのだそう。
職人は、これらの型紙を使って、模様を鹿革に写し取る準備を進めていきます。
甲州印伝の核となる漆付け技法

いよいよ印伝の特徴的な工程、漆付けの出番。
この工程では、漆を使って型紙に沿った美しい模様を、革に描いていきます。
まず、鹿革に型紙を置き、その上から生漆を盛り付けていくんです。
漆には、砥の粉や顔料、卵白などを混ぜて、少し厚みのある漆を作り、型紙を使ってそれをのせていくのだそう。
職人はヘラを使いながら、力を加減して漆を塗り広げます。
型紙を外すと、鹿革にはぷっくりと浮かび上がった文様が。
この漆の立体感が、印伝の魅力のひとつでもあります。
硬化・裁断、そして縫製による完成

漆を塗り終えたら、次は漆を硬化させるためにムロという特別な部屋で、漆がゆっくりと硬化するのを待ちます。
湿度と温度がきちんと管理され、漆は少しずつ固まり、深みのある艶が。
この時、漆の表面が非常に硬く、触るとしっかりとした手応えが感じられるんだとか。
漆が硬化したら、次に裁断と縫製。
金型で本裁ちをし、縫い代部分を薄く整えていきます。
その後、縫製作業に。
特に漆を塗った部分を縫うのは難しく、職人の技術が必要とされる繊細な作業なんです。
印伝の魅力は、こうした細かな手仕事の積み重ねによって完成します。
細部まで気を配りながら作り上げられた印伝は、どれも世界に一つだけの作品になるのです。
参考