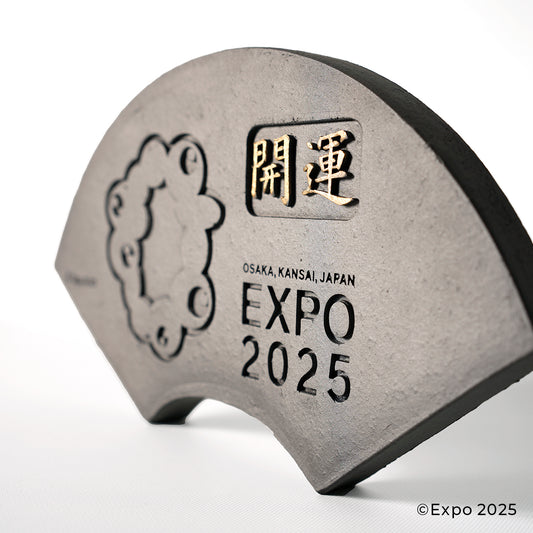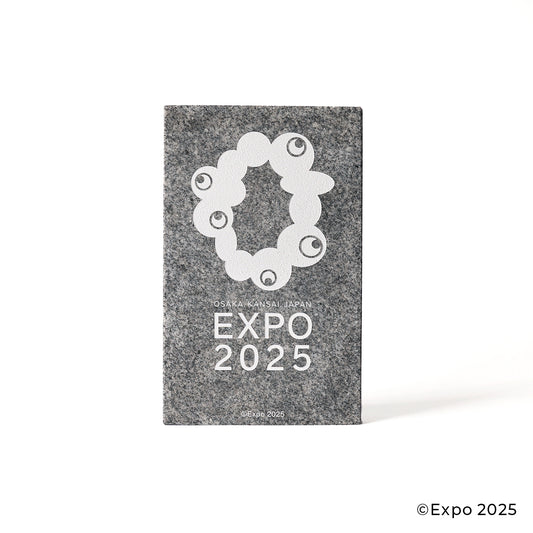田嶌さんが教えてくれた富士山ロックグラスの誕生秘話
注がれた飲み物の色で、まるで本物の富士山のように表情を変える「富士山ロックグラス」。
いまや田島硝子を代表するヒット商品として知られていますが、その誕生の裏には、
職人たちの試行錯誤と、一つの“偶然の発見”があったのだそう。
今回はその誕生秘話についてご紹介。
きっかけは「泡が雪に見えるグラス」から
最初のきっかけは、富士山シリーズの第一作「宝永グラス」

ビールを注ぐと泡が雪のように見える、台形のグラスは
ユニークな発想とデザインで話題となり、シリーズ化の第一歩となったのだとか。
続いて登場したのが、日本酒のぐい呑み「祝杯」。

逆さにすると富士山の形になる紅白の盃で、デザイン賞を受賞するなど高い評価を獲得。
ですが、これらはいずれも“富士山の形そのもの”をモチーフにした作品でした。
「どこに富士山を入れるか?」職人たちの挑戦
今でこそ、日本酒が海外でもブームになってるけれど、
やっぱり国によっては冷えたビールじゃない国もあるし、ビールの泡をいいとされてない国もある。
となると、次なる富士山シリーズで3番目はオーソドックスな形がいいのではないか、と。
だけど今までのその前の2つが形にこだわってきたからこそ
ただ絵柄で富士山を入れたって、普通のコップと変わらなくなってしまう。
そこで職人たちが目を付けたのが、グラスの“底”だったのだとか。
とはいえ、底に山の形を入れるのは容易なことではありません。
吹きガラスは竿を回しながら形を作るため、山の突起があると竿が引っかかってしまうのです。
そこで職人たちは考え抜き、特殊な金型を一から製作。
半年もの試作を重ね、ようやく理想の形が完成したのだとか。
まさに、伝統の技術に新しい発想を融合させた瞬間です。
偶然が生んだ「山肌の輝き」

完成したグラスの試作品に、ある日、麦茶を注いでみると——
その茶色い液体が薄く反射し、底の富士山の稜線が浮かび上がったのです。
それは、まるで夕日に染まる富士の姿のよう。
「この色の変化こそが面白い」
それは誰も予想していなかった、偶然の産物だったのだそう。
だけどもこの発見が富士山ロックグラスの最大の魅力となったのです。
インバウンド需要が高まっていた時代背景にも後押しされ、
富士山グラスはおみやげとしても愛されるように。
「おみやげグランプリ2014」に初出品したところ、
約500作品の中から大賞と観光庁長官賞をW受賞。
翌2015年1月に発売されたと同時に注目が集まり、
SNSでは、「ビールを注ぐと雪化粧の富士」「ジュースを入れると夕焼けの富士」といった投稿が続々と。
人々が自分の“富士山の一瞬”をシェアし、瞬く間に話題が広まりました。
拡散の波はテレビや新聞などマスメディアにも届き、
田島ガラスの名を世界へと広がっていったのです。
技術と発想、そして偶然の美しさが重なって生まれた奇跡のような作品。
底に宿る小さな富士山は、光と色によって無限の表情を見せてくれます。
それは、職人たちが積み重ねてきた手仕事の美が生み出した結晶なのかもしれません。