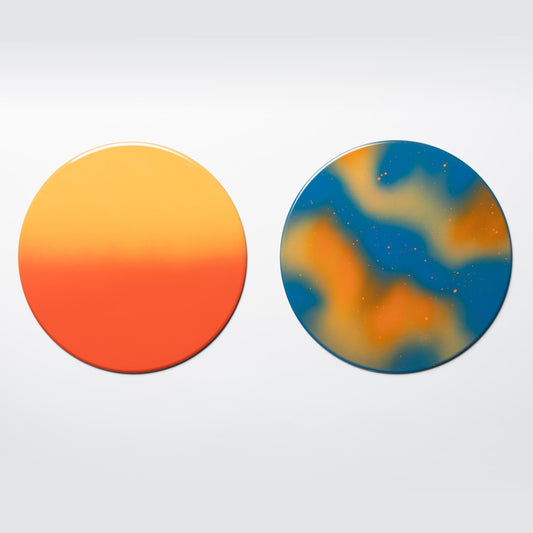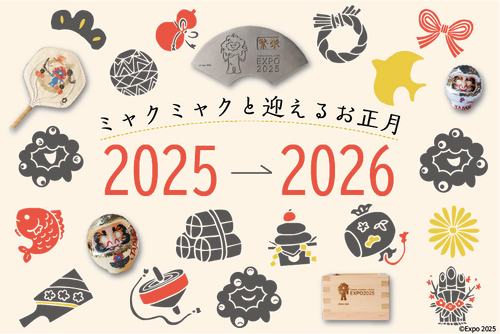枡ができるまでの12の工程

大橋量器では、70年以上受け継がれてきた技術を守りながら、
今日もひとつひとつ、丁寧に枡をつくり続けています。
ひとつの枡が生まれるまでには、
多くの工程と、職人技がぎゅっとつまっています。
今回は、そんな匠の技によって形づくられる、
枡ができるまでの工程をご紹介します。
①木材の仕入れ
まずは、木を選ぶところから。
大橋量器が扱うのは、国産の天然ひのき。
大橋量器がある大垣市は、木曽ひのきや東濃ひのきなど日本有数のひのき産地に近く、
天然ひのきを入手するには恵まれた土地なのだとか。
これら日本を代表する良質なひのきの端材(建築材などに出る切り落とし部分)を選び抜き、枡づくりが始まるのです。
② 乾燥
仕入れたひのきは、すぐには使えません。
木に含まれる水分や油分を飛ばし、樹脂成分(ヤニ)が出にくくなるよう
丁寧に乾燥させる必要があります。
乾燥方法は、
・天日干し
・燻し
・電気ヒーター
などを使い分け。
天日干しの場合、冬に仕入れた木材でも夏まで待ち、ひと夏じっくり干すことも。
枡づくりの土台を整える、とても大切な工程です。
③ モルダー加工

4軸モルダーという木工機械で、
ひのきの板の下面・右面・左面・上面の4面を同時に削ってサイズを整える工程。
1合枡だけでも、
・側板用:約1,600枚
・底板用:約400枚
合計約2,000枚を1日で整形しているのだとか。
さらに機械の出口にある「超仕上げ(カンナ掛け機)」によって、
内側になる面をツルツルに磨き上げる。
私たちが手にする枡のなめらかな手触りは、この工程から生まれているのです。
④ 駒切り(こまぎり)
モルダーで整えた板を、枡の寸法にあわせて
ジャンピングソーという機械で20枚同時にカットする工程。
一合枡の場合、側板と底板を合わせて
1日におよそ1万枚もの板をカットしているそう。
⑤ カッター

枡の四隅を組むために必要な“溝(ほぞ)”を掘る工程です。
ロッキングカッターという機械で、20枚の板を
一度の動作で左右対称に彫り上げます。
⑥ のり付け
組み立てる前に糊付け作業。
ブラシを使って溝(ほぞ)に木工用ボンドを薄く均一に。
多すぎず、少なすぎず、ちょうどよく。
この作業は職人の腕の見せ所の1つ。
大橋量器では食品衛生上問題のない木工用ボンドを使用されています。
⑦ 組み(あられ組)

いよいよ枡の形が見えてくる工程。
4枚の側板を 「あられ組」 という伝統の組み方で四角に組んでいきます。
まずは軽く仮組し、エアープレスで本締め。
一合枡は専用機械で、
一合枡・八勺枡より大きいものや小さいものは
職人の手によって組み上げられます。
最後は職人が自らの目で、
しっかり組まれているかチェック。
わずかなズレも見逃さない感覚とスピードは、まさに“職人技”の工程です。
⑧ 底付け
枡の木枠に底板を貼る工程。
糊を塗り、
・手締めで一晩乾燥
・底付け機で熱乾燥
など、サイズや用途に応じて使い分け。
ここでようやく、枡の「形」が生まれるのです。
⑨ 仕上げ削り(円盤カンナ)

枡の4面を円盤カンナと呼ばれる機械で一気に削る工程。
3枚の刃が付いている機械を使って表面を均一に整えていきます。
3枚の刃がついた円盤が高速で回転し、
表面を均一で美しい状態に整えます。
一見簡単そうに見えますが、
均一で光沢のある美しい仕上がりにするには、
職人の繊細な感覚が不可欠なのです。
⑩ 面取り
枡の角は、そのままでは鋭く手触りが良くありません。
そこで、手がんなや面取り機を使って
12か所すべての角を丁寧に丸めていきます。
手に持ったとき、口に触れたときの心地よさは、
この工程で生み出されているのです。
⑪ 焼印・レーザー・印刷
枡の個性を作る最終仕上げ。
お客様の要望・用途やデザインに応じて
・焼印:濃く、香ばしい焦げ色
・レーザー:シャープで繊細
・印刷:カラー表現が可能
これら3つの方法の中から仕上げていきます。
贈り物としても喜ばれる、名入れやロゴ入れもここで施されます。
⑫ 検品・梱包・出荷
完成した枡は、職人がひとつひとつ手と目で最終チェック。
クラフト紙でやさしく包まれ、箱に詰められると、
ひのきの香りを届けながら皆さまのもとへ届けられます。