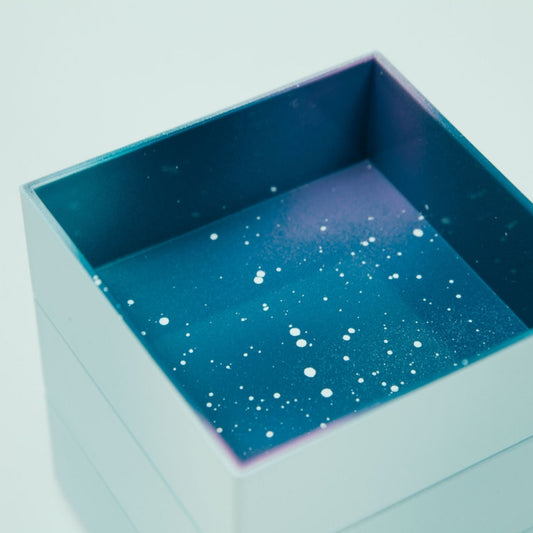「伝統的工芸品」と「伝統工芸品」の違いって?

有田焼や輪島塗、京友禅、南部鉄器――。
名前を聞いたことがある方は多いかもしれません。
でも、これらが「伝統的工芸品」として国に正式に指定されているって、
意外と知られていないのではないでしょうか。
「伝統工芸」と「伝統的工芸品」、
よく似たこのふたつの言葉には、実はちゃんとした違いがあるんです。
むずかしい話のようでいて、実は私たちの暮らしにとても身近なもの。
その違いと、ものづくりの奥深さを、ゆっくり見ていきましょう。
そもそも「伝統工芸」とは
伝統工芸とは、先祖代々の知恵と技を受け継いできた文化のこと。
その技術や技法が機械化されることなく、人の手仕事として今も続いているものたちです。
昔ながらの材料や技法を使い、丁寧に仕上げられる“美しいもの”。
長い歴史の中で磨かれてきた形や色、手触り。
それが、私たちが「伝統工芸」と呼んでいるものなのです。
「伝統的工芸品」は国が認める伝統工芸
一方の「伝統的工芸品」は、経済産業大臣が指定する特別な工芸品。
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」という国のルールに基づいて
正式に定められているんです。
この“的”という一文字には、
昔ながらの技や素材を大切にしながら、
時代に合わせて改良を重ねているという意味が込められているんだとか。
つまり、ただ守るだけではなく、
いまの暮らしにつなげていく伝統、ということなんです。
じゃあ、どうすれば「伝統的工芸品」として国から認められるのか。
それには5つの条件をすべて満たす必要があるのです。
-
主として日常生活で使われること
お祝いごとや節句なども“日常”の一部と考えられています。
使われることで“用の美”が磨かれていく、という考え方なんだとか。 -
製造過程の主要部分が手工業的であること
補助的に機械を使ってもOK。
ただし、その工芸品らしさを決める要の工程は手作業で、ということ。 -
伝統的な技術または技法によること
めやすはおよそ100年以上。多くの作り手の試行錯誤と改良の積み重ねで、現在の形が生まれてきたんだとか。 -
伝統的な原材料を主に使っていること
こちらもおよそ100年以上続く素材。もし入手が難しくなった場合は、持ち味を損なわない範囲で同種の原材料に転換してもよいとされています。 -
一定の地域で産地が形成されていること
おおむね10企業以上または30人以上の作り手がいる地域規模が想定されています。
伝統は「土地」と「人」のつながりで支えられている、ということなんです。
現在、経済産業大臣が指定する伝統的工芸品は、全国で243品目にのぼるそう(令和6年10月時点)。
陶磁器、織物、漆器、金工、木工竹工など、各地の風土が色濃く映し出されています。
「国の指定」だけが伝統じゃない、地域のたからもの
少し視野を広げてみると、国の指定がなくても素晴らしい工芸はたくさんあります。
たとえば――
・歴史が100年に満たないもの
・一度途絶えて復活した工芸
・作り手がごく少ない分野 など。
高崎だるまもその一つ。
こうした“地域のたから”は、都道府県や自治体が独自の基準で指定し、
地域文化として守り続けているんです。
つまり、「伝統的工芸品」でなくても、立派な“伝統工芸”。
地域の誇りとして、いまも息づいているのではないでしょうか。
伝統工芸の魅力
それでは、伝統工芸の魅力って何でしょうか。
どの地域のものづくりにも共通して見られる、5つの“らしさ”を挙げてみました。
糸や木、土や金属などを五感で選び、指先で確かめながら形にしていく。まったく同じものが二つとない“一点もの”の世界観。
・自然素材のやさしさ
染料や漆、竹、木、土、石――里山の贈りものとも呼ばれる素材たち。役目を終えても環境への負荷が小さいのも特徴なんだとか。
・受け継がれる技術と技法
ひとつの技を体に落とし込むには長い時間が必要。十年続けてようやく少し道が見えてくる、そんな奥行きが質感や意匠に表れます。
・感性と意匠
使う人のことを思いながら、使いやすく、長く、美しく。思いやりの心が、細部の設計や佇まいににじみます。
・伝統と新しさのバランス
伝統を守るだけでなく、時代に合わせて少しずつ進化していく。たとえば、伝統的に黒が主流だった鉄瓶に、
鉄瓶らしさを損なわない色を加える挑戦なども、その一例。
みなさんは「伝統工芸」と聞くと、どんなものを思い浮かべるでしょうか。
その答えは、どれもきっと“正解”です。
伝統工芸は、“古いもの”ではなく“いまを生きるものづくり”。
「伝統的工芸品」と「伝統工芸」は、似ているようで制度上の位置づけが異なります。
でも、どちらにも職人の技と誇りが流れていて、
使う人の暮らしの中で磨かれていく――その根っこは同じなのではないでしょうか。
「伝統的工芸品と伝統工芸品の違い」を知ることは、
日本のものづくりの奥行きを感じる第一歩。
手にとって使うたび、ぬくもりや素材のやさしさがきっと伝わってくるはずです。
参考
-
伝統的工芸品について | 伝統的工芸品産業振興協会
-
47都道府県 伝統工芸百科(丸善出版)抜粋 [2,4,6,7,9–17,20–25]
-
経済産業省 資料「伝統的工芸品(METI)」抜粋 [3,18,19]
-
工芸品を知る | 伝統工芸 青山スクエア [26–29]
- 伝統工芸ってなに?見る・知る・楽しむガイドブック|公益社団法人 日本呼応外科医東日本支部編 抜粋