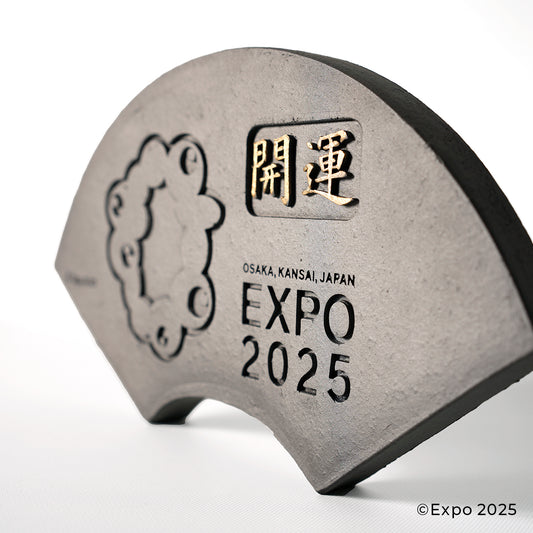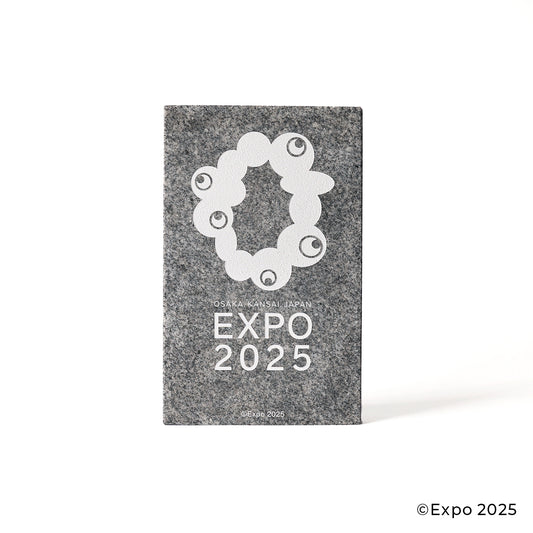390年続く長崎くんち|豪華な奉納踊と龍踊の迫力を体感してみませんか?
タグ:#イベント

長崎の秋を代表する祭り「長崎くんち」。
390年以上の歴史を持つこの祭りは、豪華絢爛な奉納踊や異国情緒あふれる演し物で、長崎の街全体を熱気で包み込みます。日本三大くんちのひとつに数えられ、国の重要無形民俗文化財にも指定されている伝統行事です。
今回は、長崎くんちの歴史や見どころをたっぷりご紹介。さらに象徴的な「龍踊」にちなんだおすすめアイテムもあわせてお届けします。
長﨑くんちの歴史
長崎くんちの起源は寛永11年(1634年)。遊女・高尾と音羽が諏訪神社で謡曲「小舞」を奉納したことに始まるといわれています。
その後、海外交流が盛んな長崎らしく、異国趣味を取り入れた豪華な祭りへと発展。江戸時代にはすでに「天下の奇祭」と呼ばれるほどでした。
昭和54年には国の重要無形民俗文化財に指定され、今日まで続く日本を代表する祭りのひとつとなっているのです。
長崎くんちの見どころ

迫力満点の「奉納踊」
長崎市内の58の踊町が7年に一度当番を務め、奉納踊を披露します。
優雅な「本踊」、巨大な船や龍を曳く「曳物(ひきもの)」、太鼓山(コッコデショ)に代表される「担ぎ物」、
大名行列のような「通り物」など種類はさまざま。
特に人気なのが「龍踊(じゃおどり)」。
全長20mを超える龍が宙を舞うように動き回る姿は、観客を圧倒します。
シンボル「傘鉾(かさぼこ)」
各町の行列の先頭に立つ傘鉾は、高さ7m・重さ150kgにもなる巨大な飾り物。
一人で担ぎながら勇壮に回転させる姿は圧巻で、町ごとに異なる装飾も見どころです。
街中で楽しめる「庭先回り」
奉納踊の後、踊町が市内を練り歩き、商店や民家の前で舞を披露する「庭先回り」も必見。
観覧券がなくても間近で演技を楽しめるため、観光客にも人気です。
掛け声とお囃子「シャギリ」
観客も一緒になって盛り上がれるのがくんちの魅力。
「モッテコーイ!(もう一度!)」の掛け声や、笛と太鼓による独特の旋律「シャギリ」は、街全体をお祭りムードに染め上げます。
有料観覧席でじっくり堪能
諏訪神社・お旅所・八坂神社・中央公園の4会場では有料観覧席が用意されます。
特に諏訪神社は人気が高く、観光客にはアクセスの良い中央公園もおすすめです。
開催概要とアクセス

開催期間:2025年10月7日(火)~10月9日(木)
会場:諏訪神社・お旅所・中央公園・八坂神社
時間:各会場・各踊町により異なります(※詳しい奉納踊のスケジュールは公式サイトをご確認ください)
アクセス:
🚃電車
- 諏訪神社:路面電車「諏訪神社」下車すぐ
- お旅所:路面電車「大波止」下車すぐ
- 中央公園:路面電車「めがね橋」下車 徒歩圏内
- 八坂神社:路面電車「崇福寺」下車すぐ
🚌バス
- 各主要バス停からもアクセス可能(「諏訪神社前」「大波止」「中央橋」など)
- 長崎自動車道「長崎多良見IC」または「長崎IC」から市内へ(※祭り期間中は交通規制あり)
龍にちなんだおすすめアイテム
ここでは長崎くんちを象徴する「龍踊」にちなみ、龍モチーフの工芸品をご紹介。
世界的な刃物の名産地として評される岐阜県関市。
その地で熟練の職人が丹精込めて作り上げた鑑賞用の美術刀剣です。
艶やかな黒塗りの鞘には、天に昇るかのような勇ましい金色の竜が描かれています。
そっと鞘から刀を抜けば、きらりと光る刀身にもまた、施工な竜の姿が現します。金色の柄巻や菊をかたどった美しい鍔など、
小さいながらも細部までにこだわり抜いた装飾は、まさに小さな芸術品。
大刀・小刀の2セットになっており、付属の掛け台に飾ることで、お部屋に格調高い和の空間を演出します。
ご自宅のインテリアとして、また歴史や日本文化がお好きな方への贈り物、海外の方へのお土産に最も最適な逸品です。