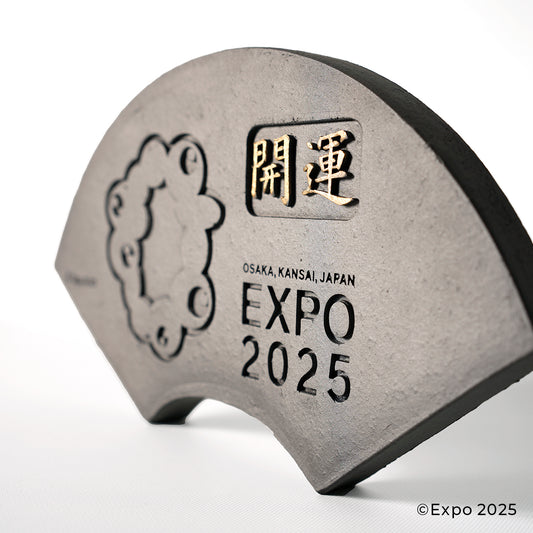”一発勝負”に懸ける想い。文化財も手がける神仲4代目・神谷琢さんという人
愛知県高浜市にある窯元「神仲(かみなか)」。
大正8年の創業から100年以上にわたり、鬼瓦の製造をはじめ、寺院などの文化財、洋風瓦など、幅広い瓦づくりを行っています。
その4代目として現場を支えるのが、神谷琢さん。
神谷さんが勤める神仲では、ほぼ全員が製造や出荷業務に携わり、
営業や組合活動、SNS発信にもチカラを入れる等、伝統と現代をつなぐそんな存在。
今回はそんな神谷琢さんの普段の仕事や日常をご紹介します。
2児の父であり、100年の伝統を守る人

| 名前 | 神谷 琢(かみや たく) |
| 生まれ | 愛知県 高浜市 |
| 扱う工藝品 | 三州鬼瓦工芸品 |
| 肩書 | 神仲 4代目 代表取締役 |
| 資格 | 愛知県鬼瓦技能評価認定試験 中級 |
「若社長」と呼ばれて育った子ども時代
神谷さんの子供のころの夢を伺うと、夢はなかったとの答えが。
その理由は、代々家業を継ぐという流れがあり、幼いころから“若社長”と呼ばれて育ったからなんだとか。
将来的には家業を継ぐという想いを持ちながら、大学は東京へ進学。
卒業後は名古屋で不動産関係の仕事に就き、4年間勤務しました。
そして27歳のとき、家業へ戻ったのだとか。
家業に戻るきっかけとなったのは、2011年に起きた東日本大震災でした。
当時は名古屋の会社に勤めていましたが、震災の影響で屋根修理の依頼が急増。
出荷が追いつかないほどの忙しさになっていたんだそう。
そこから不動産業を退職し、家業である神仲へ。
現在は、鬼瓦や特注瓦の製造にも携わっています。
瓦は成形して乾燥させて焼き上げる過程で10%ほど縮みます。
乾燥の仕方や焼き方でねじれも出るので、特注品は一発勝負なんです。
今までの経験を生かして縮みやねじれを読んで、計算通りに仕上がったときにやりがいを感じます
一枚の瓦に込められた経験と勘。
その積み重ねが、100年を超える神仲の伝統を支えているのではないでしょうか。
現場に合わせて動く、神谷さんの1日

神谷さんの1日のスケジュールについてうかがいました。
朝は5時半に起床し、朝食はとらずにコーヒーを一杯。
車で10分ほどの距離にある会社へ向かいます。
始業は8時。それまでに従業員との連絡や、人員配置を済ませ、現場がスムーズに動けるように準備をします。
日中は依頼された図面や資料を作成したり、営業や見積を行ったり。
毎日違うことをしているから、1日として同じ日はないんだそう。
仕事を終えるのは19時頃。
終業後は瓦組合関係の会合などに参加することも多く、
三州瓦協同組合伝産部会の会長を務めるなど、複数の組合活動にも関わっています。
SNSで伝える「瓦の本当の魅力」
瓦造り以外にもチカラを入れているのがSNS
東日本大震災のあと、”瓦屋根が家を押しつぶした”というような報道が流れ、
あらぬ誤解が広がりました。実際は、家自体が老朽化していたケースが多かったんだとか。
瓦は塗装も要らないし、何十年も持つ。
ハウスメーカーからすると仕事にならないくらい丈夫なんです
こうした正しい知識を伝えるため、そして瓦業界に少しでも関心を持ってもらえるようにと
組合のSNSアカウントを活用して神谷さん自ら積極的に発信しているのです。
普通の時間がいちばんの幸せ
神谷さんの休日の過ごし方について伺いました。
お客さんとゴルフに行くこともあれば、趣味のアニメやゲーム、Netflixを観たり、
冬にはスノーボードへ出かけることも。
小学生の子どもが2人おり、毎日受験勉強を教えるのが日課。
仕事に集中できて、普通の時間を過ごせるのも家族のおかげ。いつも感謝しています
お子さんの面倒を見る時間が楽しいともお話ししてくださいました。
そして、仕事を終えたあとに訪れる、もうひとつの特別な時間があります。
大型連休前の最終日従業員が全員帰ったあとは、無事一定期間走り切れた達成感と安堵した気持ちでものすごい多幸感に包まれます。
勤めていた時も最終日は嬉しかったですが今とは比べ物になりません。
静まり返った工場で味わうその瞬間は、
きっと、神谷さんにとって“責任を果たした人だけが知る幸福”なのだと思います。
家族と仲間に支えられながら、100年を超える伝統を未来へつなぐ神谷さんの姿は、
まさに "瓦とともに生きる人”そのものでした。